残像と瞳について
それぞれに対立するよう物を配置すると、例えば私達の場合なら青に対して黄/赤を置いてみます。すると双方の間に諸力がどのように織り合い関係し合っているのか説明することができます。混合した緑はすでにその一例です。
しかしまた色たちを、それぞれが依存し挑み合うことで動きや振る舞いとして現れる、一種のコミュニティに生きる存在として殊更に眺めることもできます。
アマチュアであれ絵を描く人なら誰でも、このことを次のような体験としてたどることができます。緑や青の色合いばかりで風景画を描いていくと、突然、赤とか温かい茶系の色味を補いたい強い欲求(または願望)を感じます。この必要性は色彩心理学の単純な問題ではありません。赤は現実に緑をもっと緑にします。別の言い方をすれば、完全に緑のムードの中にいると、赤とか茶色を体験しない限り、私たちは緑を失ってしまうでしょう。
色は特にこの補色作用において、それぞれがお互いを必要としています。残像体験はその明らかな証拠です。我々の目が生み出した補色の像は、幾分影を帯びた面ならどこでも投写することができます。このいわゆる「残像」は、実際のイメージを見た後で少し時間が経ってから現れ、多かれ少なかれ像が定着した後で間もなく消えていきます。
同じ理由から、もし暗闇や影がなければ、我々は光を体験することができません。両者はそれぞれ実像に対する残像と同じ関係にあります。もし真っ暗な部屋にしばらく佇んでいるなら、何らかの光が目から生み出され、瞳が極端に大きく開きます。しばらくするとその新しい光の中で私たちは再び見始めます。
瞳は双方、つまり実像と残像が出合う場所なのです。実像はもちろん残像と交差することはありません。なぜなら応答として構築される残像が、その道を戻っていくのに時間がかかるからです。しかし筋肉である瞳(実際には虹彩)は休みなくはたらき続け、闇で光に応答(集中)し、また光で闇に応答(拡大)しつつ動いています。この時点で一種の呼吸が考えられます。
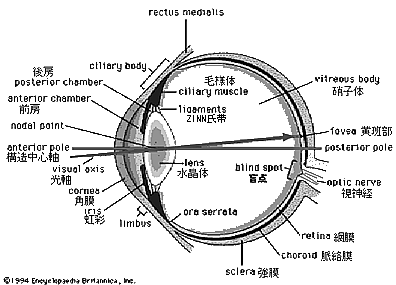
残像は外へ流れ、短い(ほとんど意識されない)輝きの後、この外界で死を迎えます。
反対にあらゆる(知覚)イメージは、人の魂のなかで新たな命となることを切望し、内側へと流れていきます。それらの像は記憶の中のスピリチュアルの次元に生まれ変わります。
多くの言語霊がこの器官を子ども時代の源とみているようです。「瞳(Pupil)」は明らかに(小さな)子供と明らかな関係があります。英語と仏語では「Pupil」に学童という意味があります。仏語の「le pupille」は里子ですが、人形(la poupee)とも関連しています。
実際に瞳は、またの名を「虹の肌」とも言う虹彩の中心部にあたり、外界の光の状況に応じて絶え間なく揺れ動きながら、バランスを見出すために生体が補色を生み出すのを許しています。しかし光の明暗ばかりに応じるだけでなく、知覚したあらゆるイメージが反転(上下左右)し、網膜に到達します。(続く)
トップページへ
a:2224 t:1 y:1